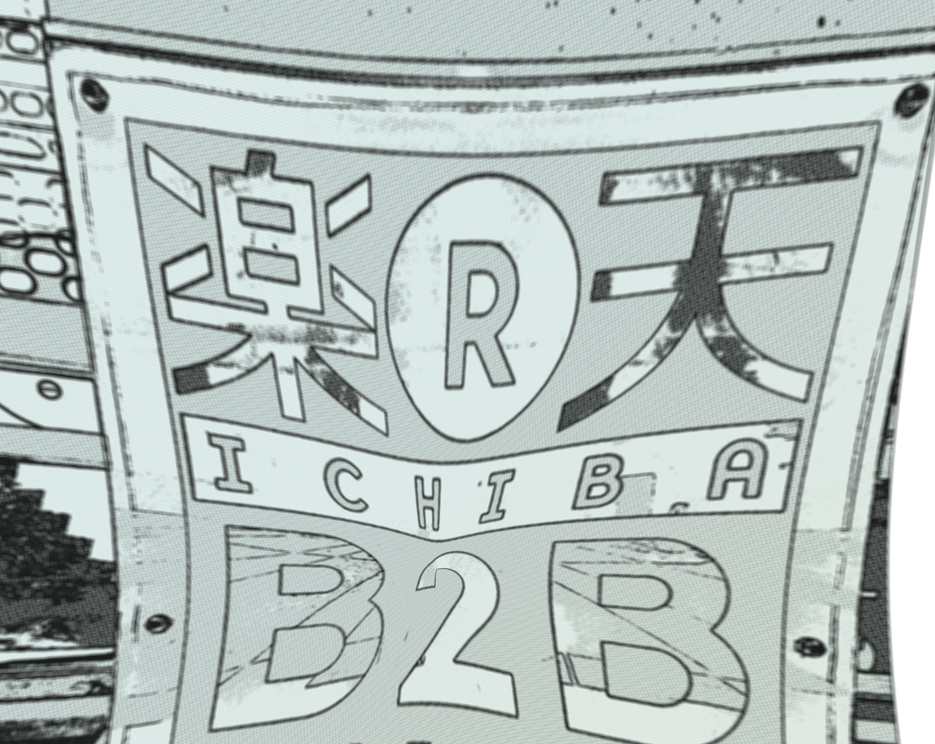楽天グループ株式会社の2025年第1四半期決算は、一部セグメントでの好調な業績にもかかわらず、全社的な収益性に依然として大きな課題を抱えている状況を浮き彫りにしています。今回は主要な財務指標に焦点を当て、同社が直面している問題点と今後の見通しについて掘り下げます。
目次
全体業績:増収も最終赤字は拡大
2025年第1四半期の連結業績を見ると、売上収益は562,704百万円(前年同期比9.6%増)と順調な成長を遂げています。また、Non-GAAP営業損失も305百万円(前年同期は25,449百万円の損失)と大幅に改善しました。
しかし、最も注目すべき点は、四半期純損失(親会社の所有者帰属)が73,471百万円(前年同期は42,394百万円の損失)と大幅に悪化していることです。この損失拡大は、営業利益の改善にもかかわらず、営業外費用や金融費用、一過性費用などの影響が大きいことを示しています。
各セグメントの明暗
インターネットサービスセグメント:安定成長
インターネットサービスセグメントは、売上収益305,478百万円(前年同期比6.9%増)、セグメント利益13,179百万円(前年同期比25.8%増)と増収増益を達成しました。主力サービスである『楽天市場』は、前年がうるう年だった反動や天候不順による影響があったものの、流通総額と売上収益が成長し、マーケティング効率の改善も相まって、利益貢献度を高めています。
物流事業においても、2024年に開始した「Rakuten最強翌日配送」導入店舗の広がりによる配送量増加と配送単価の上昇により、収益改善が進んでいます。海外事業では『Rakuten Kobo』の新型カラー対応端末の売上好調や『Rakuten Viber』の利用者増加が利益拡大に貢献しています。
フィンテックセグメント:グループの主力収益源へ
最も好調なのがフィンテックセグメントで、売上収益223,579百万円(前年同期比15.6%増)、セグメント利益43,888百万円(前年同期比21.7%増)と大幅な増収増益を達成しています。カード、銀行、証券、ペイメントの各サービスが軒並み好調で、特に銀行サービスでは日銀の政策金利引き上げに伴う運用利回りの向上により資産運用収益が拡大しました。
このフィンテックセグメントは、グループ全体の利益を大きく下支えする収益源となっており、今後の経営戦略において一層重要性を増しています。
モバイルセグメント:依然として最大の課題
一方、モバイルセグメントは、売上収益が110,705百万円と前年同期から約10%増加したものの、Non-GAAP営業利益は-51,276百万円と大幅な赤字が続いています。特に問題なのは、減価償却費が44,801百万円と高水準であることで、設備投資負担が収益性を圧迫し続けている点です。
モバイル事業は契約者数が増加傾向にある一方で、設備投資は前年同期比-59.3%と大幅に抑制されており、短期的なキャッシュフロー改善を優先する姿勢が見られます。しかし、この投資抑制が長期的な競争力に与える影響については注視が必要です。
財務状態:悪化する財政基盤
自己資本比率の低下
親会社所有者帰属持分比率は前期末の3.5%から3.3%へと低下し、資本合計も26,514,728百万円から25,077,197百万円へと減少しています。これは、継続的な最終赤字による利益剰余金の減少が主要因と考えられます。
キャッシュフローの急速な悪化
最も憂慮すべき点は、キャッシュフローの状況です。営業活動によるキャッシュフローは-737,720百万円と大幅なマイナス、投資活動によるキャッシュフローも-283,210百万円、財務活動によるキャッシュフローも-223,851百万円と全てのキャッシュフローがマイナスとなり、3ヶ月間で現金及び現金同等物が1,252,419百万円も減少しています。
この急速なキャッシュ流出は、本業からの資金創出力の不足と、多額の投資・借入金返済の両面から来ており、今後の事業運営に大きな制約を与える可能性があります。
今後の見通しと課題
楽天グループは、証券サービスを除いた連結売上収益について前期比二桁成長を目指すとし、Non-GAAP営業利益の黒字化も目標として掲げています。各セグメントでも積極的な成長戦略を描いていますが、実現のためには以下の課題への対応が不可欠です。
- モバイル事業の収益改善:契約者数増加とARPU(顧客単価)向上の両立、および設備投資の最適化
- 有利子負債の削減:資本効率の改善と金融費用の低減
- キャッシュフロー体質の強化:本業からの持続的なキャッシュ創出力の回復
- グループシナジーの実現:エコシステム内での相互送客効果の最大化
まとめ:収益構造改革が急務
楽天グループの2025年第1四半期決算からは、インターネットサービスとフィンテックが堅調な一方で、モバイル事業の赤字継続と急速なキャッシュ流出という二つの大きな課題が浮き彫りになりました。
特に親会社所有者帰属持分比率が3.3%という低水準にある中、キャッシュフローの急激な悪化は財務基盤をさらに弱体化させるリスクがあります。今後の収益構造改革と資本効率の改善が、同社の中長期的な成長において最重要課題と言えるでしょう。
フィンテックセグメントの好調な業績を足掛かりに、グループシナジーを最大限に活用しながら、モバイル事業のコスト構造改革を急ぐことが求められます。投資家は特に、今後の四半期におけるキャッシュフロー状況と有利子負債の推移に注目する必要があるでしょう。